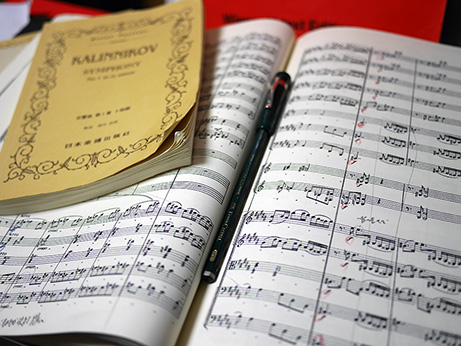
Part1では、カリンニコフ本人の手紙のリーディングを通じて、交響曲第1番執筆時の彼の状況や思考を立上がらせることを試みた。ロシア語からの翻訳ということで私には十分に訳しきれなかったところが多かったかもしれないが、交響曲第1番に彼の人生が深く刻まれているということは疑いないものになったように思う。Part2では、交響曲第1番を作曲していたころと並行する時期の彼の楽曲を見ておきたい。とりわけ、ピアノ4手による「交響曲第1番の主題によるポロネーズ」(Полонез на темы Симфонии No. 1)、および歌曲(たとえばアレクセイ・プレシチェーエフの詩によるНам звёзды кроткие мерцали)が重要になるだろう。



